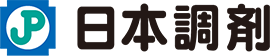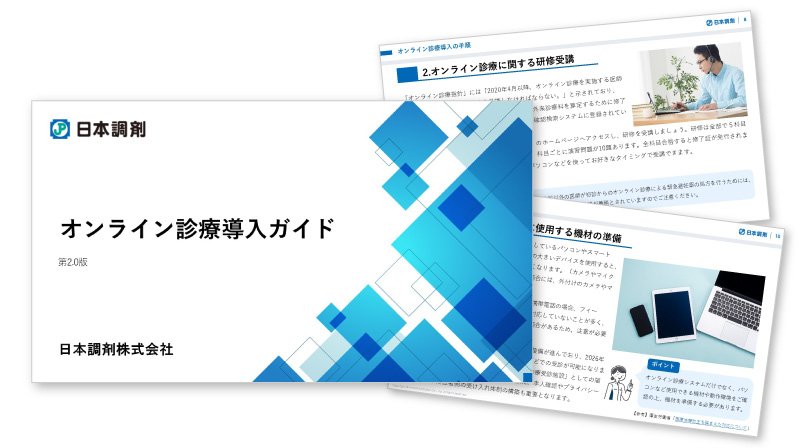1977年から地域に根差した医療を行っている大田屋クリニックの2代目の佐藤 孝典先生は、2020年のコロナウイルスが流行した頃からオンライン診療を始め、多くの患者さまをオンラインで診ています。今回は、オンライン診療を運営するコツや、オンライン診療を始めようとしている方へのアドバイスをうかがいました。
※肩書・ご活動の状況などはインタビュー当時(2024年1月)のものです。
オンライン診療を回せる枠組みを作ってシステム化して回していく
――オンライン診療をはじめたきっかけを教えてください。
オンライン診療は最初の頃はかなり厳しい規制があり、とても出来そうにありませんでした。コロナで規制が緩くなった頃に、ちょっとやってみようという話になり、オンライン診療ツールを導入してみたというのが始まりです。
――最初はGoogle meetを利用していらっしゃいましたよね?
はい。はじめは自前のものでスタートして、試行錯誤しながら感触をつかんでいった感じです。段階的にやりやすい方法に変えていきました。
――現在はどのようにオンライン診療を行っていますか?
当院の場合、私がオンライン診療を行っている横に医療事務スタッフについてもらって、パソコンでの入力作業や次の患者さまの準備を行ってもらっています。前の患者さまの診療を行っている間に次の患者さまのオンライン診療をつないでもらっていて、分業することで効率化しています。
――そうすると、他の先生が始めるとしたら、まず医療事務の方がオンライン診療やシステムに詳しくないといけないでしょうか。
クリニックの運用に合わせてオンライン診療を回せる枠組みを作ってシステム化してしまえば、あとは回すだけだと思います。全部医者がやろうとしてもうまくいかないので、医療事務の方と連携して分業した方がいいと思います。当院も何段階も改善して今のやり方に至っています。
――オンライン診療を希望される患者さまはどんな方が多いですか?
90日処方の患者さまは結構多いです。血圧の薬の3ヵ月処方の患者さまで、薬をもらうために2時間待って診察は3分になってしまうこともあるので、そういった患者さまにはオンライン診療を勧めています。なるべく待たせたくないという思いがあるので、オンラインに慣れている若い患者さまにはオンライン診療と対面診療を交互に受診するようお勧めしています。大体の方がオンラインに移行されます。
オンライン診療希望の患者さまは、医師と話をしたいというよりは、いつもの薬をもらうのに、時間をかけずになるべく手短に、効率よく薬を処方してもらいたいと思っている方が多いので、1人にかかる時間は短いですね。
――現在、何時~何時までオンライン診療の予約を入れられるのでしょうか?
大体、午前の診療が終わる頃と午後の診療が終わる頃に入ります。予約の枠は制限しています。
オンラインでしかできない医療がある
――オンライン診療の症例を教えていただけますか
オンラインでしかできない医療もいくつかあります。お一人はパニック障害で不安が強すぎて、家の外に出られなくなってしまい市に相談したら、当院にオンライン診療を頼むようにと言われたそうです。その時はとても玄関から出られない状態で、オンラインで薬を出していましたが、今は普通に来てくれています。
他には、在宅医療機器を使用している心臓が悪い方で、毎年娘さんの家に滞在する2~3ヵ月間だけオンライン診療をしています。その時期だけ他の医師を受診するよりは、かかりつけ医を受診したいと、オンラインを選択していただきました。
あと、以前は当院の近くに住んでいて通院されていた患者さまで、引っ越した後もオンラインで受診されるている方もいらっしゃいます。オンラインでも当院をかかりつけとして、ご利用される患者さまも結構いるんですよね。そういった方には、本当に具合が悪いときは、ご近所の病院へ行かれるようにお伝えしています。
オンライン診療で収益を増やすポイントは、1人当たりの時間を減らして、満足度をキープすること
――他の医師からオンライン診療について相談を受けることがありますか?
そうですね。色々なところで聞くのは、「医者の仕事量が増えて、収益が減るのはおかしいんじゃないか」っていう話が多いですね。それは運営の仕方によるところが大きいでしょうね。3時間で何人を診るかなので、1人当たりの時間をどうやって減らしてどうやって満足度をキープするのかですね。オンライン診療に移行できる方がその中に何人かいると、他の患者さまに時間を割けます。医者が全部やるわけではないので、少し安くなっても患者さまを回せるなら全く問題はないと思います。
最初は当然、収益化のことを考えて1か月に1回の診療としていました。しかし、医者1人で診られる患者さまの数にも限りがあります。処方日数を長くしても満足していただけるなら、1ヶ月に1回の診療よりも3ヶ月に1回の診療の方がいいですからね。

オンラインの一番の弱点は、相手の背景が分からないこと
――オンライン診療が向いていない患者さまは、どういった方でしょうか?
スマートフォンを使い慣れていないという方もそうですが、対面での受診を好まれる方もいらっしゃいます。
また、オンラインの一番の弱点は、相手の背景が分からないことです。全国からさまざまな患者さまが来るので、医薬品の適切な使用ができないと判断した場合には、お断りする場合があります。
オンライン診療が実施できるかは、受付時にチェックをするようにしており、スタッフから相談があった際には、患者さまに対面診療をお願いすることもあります。オンラインも万能ではないので、本当に具合の悪い方などにはすぐ来てほしいと思っています。オンライン診療後、発熱症状でやっぱりコロナとインフルエンザの検査をしたいと途中から気持ちが変わった場合も、近くの方には来てもらっています。そういったケースでは、オンラインで検査内容を相談して、その後、検査のために来院をしてもらい効率化を図っています。
どうしても医療者の持っているオンライン診療のビジョンと、患者さまの持っているビジョンが異なることがあります。患者さまは何でも診てもらえると思っていますが、これは向かないとか明らかに具合が悪いとか、オンラインで対応困難な疾患もあるので、事前のWEB問診でチェックして、専門の診療科の受診をすすめることや、直接来てくださいとオンラインを断ることもあります。
オンライン診療の導入でネックになるのは「支払い」
――オンライン診療の導入で難しいと感じられることはありますか?
オンライン診療の導入でネックになるのはやはり、支払いについてでしょう。クレジットカードや電子決済、Paypayなどの電子マネーが普及したことがバックグラウンドにありますが、こういったサービスを、ある程度年配の方でも利用されることが増えてきているため、医療機関側が対応していない場合、支払いの問題が出てきてしまうという背景もあるでしょう。中高年の方もスマートフォンを持っていますし、バックボーンや背景が揃えば、オンラインも充実してできると思います。60代の方も普通にやっていますからね。でも、どうしても現金払いしか出来ない方には、オンライン診療後に、窓口に来て支払いと処方箋受取りという流れも選択できるようにして、幅広い世代が利用できるようにしています。
――クレジットカードを使われる患者さまはどのくらいいらっしゃいますか?
集計をしないと分かりませんが、結構多いと思います。当院はQRコード決済、電子マネー決済、iD決済など全てOKにしています。訪問診療などでは口座引き落としです。
オンライン診療の支払いはクレジットカード決済のみです。
しっかりと役割分担をすることで、医師の仕事が減る
――最近、他の医療機関から、「とにかく外来が忙しくてオンライン診療をやる時間がない」とか、「準備をする余力がない」というお問い合わせをいただくことがあります。
私はオンラインの方が、診療も早く終わるのでありがたいです。医者以外のスタッフも人数を絞り、人件費を抑えた運用をしている医療機関は、オンライン診療を実施できる体制を作ることが難しいかもしれないですね。
――なるほど。オンライン診療を行う体制づくりに課題があると感じますが、そういった医療機関にはどのようにアドバイスしますか?
結局のところ人件費が高いのは医者なので、業務分担をして医者の仕事を減らすことがポイントだと思います。
オンライン診療で他のスタッフにも役割を担っていただくことで、医者の仕事が減ることによって、結果的に収益は増えると思います。
対面の場合、「先生、もう一つ聞いてもらいたいことがあるのですが・・・」といった患者さまもいらっしゃいますが、オンライン診療の患者さまは、診療をコンパクトに終わらせたい方が多いので、短時間で診療が終わりますね。医者にとっても患者さまにとっても時短になっていると思います。『2時間待って3分で終わる』医療って、自身が患者だったらきついと思います。病院で2時間かかった後、その患者さまは会計を待ち、調剤薬局でも待ったら、それで半日かかってしまいます。それだったら、症状が落ち着いてる患者さまにはオンライン診療の方がいいと思いますね。オンラインが向いている方はオンライン診療、向いていない方は対面診療。必要に応じてハイブリッドで診療する方は結構多いです。例えば、甲状線やリウマチなどで同じ薬を継続している方とかも、普段はオンライン診療を行い、「たまには採血して検査をする必要があるので、対面診療を」という感じですね。
――オンライン診療のサポートをしている医療事務の方は、どのような方ですか?
当院の場合、クリニックをリニューアルをした当初は、サポートについてもらうスタッフはおりませんでしたが、混雑してきたため、医療事務スタッフにサポートしてもらうことになりました。受付などの流れも把握している医療事務に、オンライン診療の手伝いをしてもらうシステムです。別途専任のスタッフを雇うというよりは、受付ができるスタッフに、今日の業務は受付ではなく、オンライン診療のサポートに入ってもらうというような運用です。医療事務歴が長くても、パソコンが苦手なスタッフは難しいかもしれません。当院では、パソコンを使えるスタッフが担当しています。
――オンライン診療をまだ始めていない先生から「オンライン診療もきっとデメリットとか色々あると思うから、それを全部明らかにしてからじゃないと、自分は怖くて始められない。」という声を聞くことがあります。
医師の中でも、既存のやり方を継続したい方と、新しい医療に取り組んでいきたい方がいらっしゃると思います。もちろんオンラインのデメリットもあるとは思いますが、『2時間待って3分で終わる』医療を改善するために、新しいやり方にチャレンジできるかどうかだと思います。
私の場合は、例えばコレステロールの薬や尿酸の薬を継続している患者さまが、毎月受診をする際に2時間待って3分で終わる医療をずっと継続することは「何か違う」と考えています。患者さま1人1人に合うやり方を提案していきたいです。
オンライン診療を始めるのが不安な先生も、まずは初診はオンライン対応をなしにして、再診のみで、オンライン診療に合う患者さまをリクルートしていくのがいいと思います。

患者さま1人にかけられる時間が短くなってきたら、工夫をしなければ患者さまは去っていく。改善方法の一つがオンライン。
――これからオンライン診療を始めようとしている医師へメッセージをお願いします。
オンライン診療については、実際に取り入れてみたら非常に良いものでしたし、オンライン診療が向いている患者さまから始めることで、患者さまの数も増やせると思います。もしコスト面に悩んでいるのであれば、1件の対応にかかる時間を短縮できる運用を構築することで、成り立つのではないでしょうか。
当院の場合は、ある程度患者さまの数が増えてきておりますので、限られた時間の中で、どれだけたくさんの患者さまが当院に来ていただけるかという考え方で運営しております。
私は、処方日数を伸ばすことで、診療のクオリティを高める方にシフトしました。たくさんの人に来てもらった方が母体は大きくなると思っていますし、受け皿を広くするにはそれしかないので、それでいいかなと考えています。患者さまおひとりの診察にかかる費用ではなく、時間を有効活用するという考え方であれば、1回の診察にかかる時間を短くし、全体で診療可能な人数を増やせることにつながります。
私も色々悩みましたが、長い処方で費用面でも安く済むのであれば、長時間お待ちいただいた患者さまも納得してくれるかな、と考えています。患者さまの満足度が高いことが、患者さまがクリニックから離れない要因になります。
医者の熱意が高く、クリニックも空いているうちは、医者がしっかり説明をする時間もとれますし、『いい医療』を続けていれば、当然、患者さまが「ここのクリニックいいなぁ。また来よう。」と思ってくれますが、混雑してくると状況が変わってきます。
一人の患者さまに割ける時間が15分 → 10分 → 5分と短くなってくれば、患者さまの満足度も下がっていきます。あとはクリニックの運営を工夫するしかないという話になってくると思いますが、その改善方法の一つがオンライン診療です。
さきほどお伝えした『リクルートした患者さまだけ、オンライン診療を行う』というのも一つの方法ですね。『2時間待って3分で終わる』医療を改善するためにチャレンジすることが大切だと思います。
病院情報
大田屋クリニック
URL: https://ootayaclinic.com/
住所:山梨県富士吉田市上吉田5-8-3
プロフィール
佐藤 孝典
大田屋クリニック 院長
専門:循環器内科
北里大学医学部卒業。日本循環器学会 専門医。
大学卒業後、静岡病院、北里大学病院、富士病院、富士吉田市立病院などに勤務後、大田屋クリニックに非常勤で勤務。2018年に大田屋クリニックをリニューアルして2020年より2代目として院長を務める。
「患者さまの立場に立ち、ともに歩んでいくクリニック」という理念のもと、土日診療やオンライン診療を提供している。(敬称略)