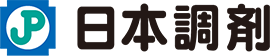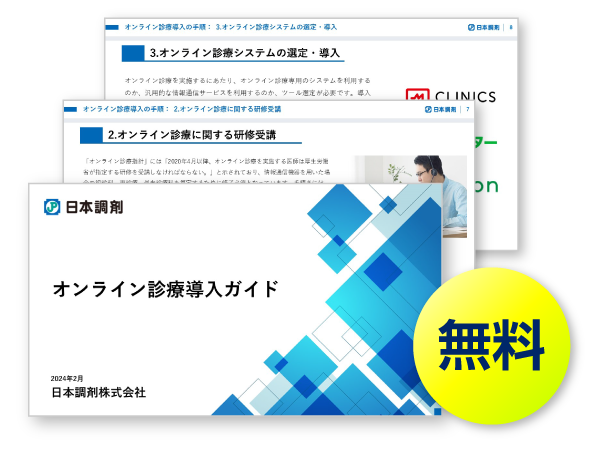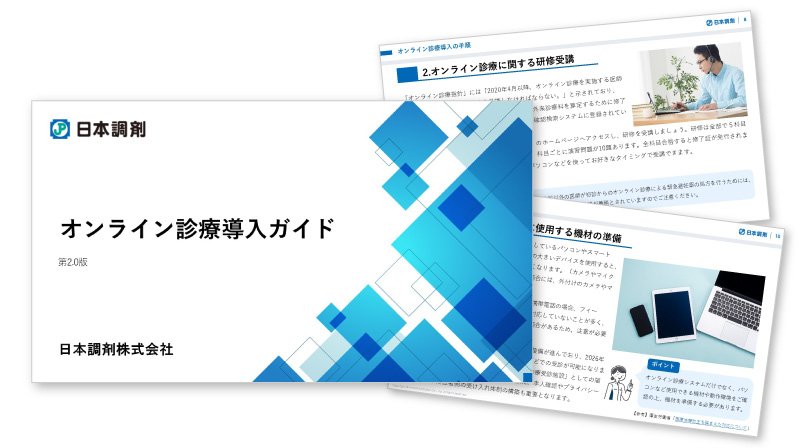患者さまに幅広い治療を提供するには、自由診療や保険診療の違いを理解しておく必要があります。公的制度で全額負担されない先進医療や歯科の一部行為は、患者さまにとって費用面で大きな負担になり得る場合があります。しかし、それぞれのメリットやデメリットを把握し、自己方針と安全を両立する方法を考えることで、患者さまの経済的リスクを抑えながら最適なサービスを提供できます。本記事では、がん保険や高額医療の併用など具体的なケースも解説し、診療所やクリニックで役立つポイントを整理します。
公的保険の対象外となる先進技術の使用や、自己負担割合が大きい手術を選ぶ理由にも注目してください。厚生労働省が承認する制度を正しく理解し、貴院の方針を柔軟に決定しましょう。
日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた
「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。
自由診療とは?
健康保険等の公的医療保険が適用されない医療技術や薬剤を使う診療は自由診療と呼ばれます。保険外のため費用は全額(10割)が患者さまの自己負担となり、負担割合は通常の診療である保険診療の原則3割負担より大きくなります。自由診療を行えることは、負担額は多くなりますが患者さまにとっては、治療の選択肢が増える点が大きな利点です。公的保険制度では認められていない先進的な技術の使用も可能なので、美容や歯科など幅広い分野で柔軟な治療が期待できます。
一方で、厚生労働省が承認していない方法は安全性や効果の評価が十分でない場合があるので、あらかじめ医療機関も診療内容や価格設定などを決定しておく必要があります。たとえば海外で認められていても日本では未承認の治療は保険適用外になります。費用負担が大きい分、経済面での問題につながるケースもあるため、事前の患者さまの説明と納得が欠かせません。自由診療を検討いただく際は病院やクリニックの方針を定め、患者さまにとって最適な治療かどうかを見極めることが大切です。公的医療保険との違いを正しく説明し、自己負担が増えるリスクも踏まえつつ十分に検討いただけるようにしましょう。
自由診療が必要なケースと保険適用の範囲
保険診療は国民健康保険や健康保険などの制度により定められた診療を指します。どの医療機関でも同じ基準で治療を受けられるため、検査や治療内容が統一されています。患者さまの自己負担は原則として一定の割合なので、費用面での負担軽減が期待できます。ただし、保険診療の範囲外となる先進的な治療や整容のみの処置などは自由診療に該当する場合があります。自由診療が必要なケースとして、日本で未承認の治療を望む時や、美容上の悩みを深く相談したい時などが挙げられます。保険診療内で十分な効果が得られない場合に、自由診療を検討する選択肢もあるでしょう。公的保険の適用範囲と自由診療には違いがあるため、患者さまと相談しながら内容を確認し、負担に見合うと思っていただける治療方法を考え、提案をすることが不可欠です。必要に応じて高額療養費制度なども活用しながら、患者さまの経済状況や治療の目的を踏まえて検討すると安心です。
自由診療を選択するメリットとデメリット
公的保険が適用されない治療も選べ、診療の幅が広がることが大きなメリットです。患者さまの体質や美容面の悩みに合わせた独自の治療方法が提供できることで集患(集客)につながります。先進技術の活用で最新の手術や薬を使える可能性も高まり、時間をかけたサービスが提供できるケースもあるでしょう。また、価格を独自に設定できるため保険診療に比べて高い利益率が見込めることもメリットとなります。
デメリットとしては、自由診療のみとした場合に経済面で患者さまがふるいにかけられてしまう点が挙げられます。自由診療だからといって高い価格設定をしてしまうと患者さまの選択肢から外れてしまいます。今はインターネットで簡単に情報も収集できますので、競合の医療機関と比較されてしまうことに注意しましょう。また保険診療と比較して、エビデンスが十分に確立されていない治療法も含まれるため、患者さまは効果に不安を感じている場合があります。そのため、しっかりと診療方針や安全性などの説明を行い、患者さまの不安を解消させ、診療を受けていただくことが重要です。説明が不十分であるとトラブルにつながることもあるので十分注意しましょう。
保険診療との併用はできる?
保険診療と自由診療の併用(いわゆる混合診療)は原則として禁止されています。保険診療は国民健康保険や健康保険など公的保険制度による診療を指し、日本全国で同じ内容の治療に対して同じ点数が適用される仕組みです。病気やケガで受診する場合、保険証を提出しておけば費用の一部を負担するだけで治療が受けられるのが基本です。自由診療の項目を追加すると保険診療部分も自由診療とみなされ全体が保険適用外となります。高額療養費制度や各種給付金が利用できるのは保険診療部分に限られるため、保険診療内で対応できる症状かどうかを判断することが重要です。必要以上に範囲を広げると予想外の経済的負担を患者さまが負う可能性もあるため、適用範囲と範囲外で価格、診療内容がどう変わるか説明し、患者さまと治療方針を決めましょう。
保険診療で自由診療の一部のみ適用されるケースとは?
保険診療と自由診療には明確な違いがあります。保険診療の場合、検査や治療内容が原則として定められており、自己負担が3割ほどで済むなど負担が軽減されます。一方、自由診療(保険外診療)では公的保険を使用せず、治療費はすべて患者さまが支払います。ただし、症状や治療方法によっては保険診療と自由診療を部分的に組み合わせるケースが認められることもあります。たとえば、一部の検査や薬剤が保険で認められない場合でも、保険適用が可能な部分と自由診療部分を分けて行うことがあります。しかしながら、その適応条件は厳しく、医療機関側もルールに沿った対応が必要です。
厚生労働省が保険診療と自由診療(保険外診療)の併用についてをまとめておりますので下記もぜひご参考ください。
【参考】厚生労働省「保険診療と保険外診療の併用について」
オンライン診療導入ガイド
【こんな方におすすめ】
- オンライン診療の導入を検討している
- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい
- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない
がん保険や先進医療など自由診療で活用可能な選択肢
公的保険制度だけでは治療法が限られると感じる場合、がん保険や先進医療などの自由診療が選択肢となることがあります。特にがん保険に加入していると、入院給付金や手術費用の一部をまかなえる可能性もあります。ただし、公的医療保険を前提にした保険商品が多いため、自由診療にかかる費用がすべて補償されるわけではありません。病院やクリニックで先進技術を利用する際は、高度な設備や海外で先に承認されている治療方法を受けられるメリットもありますが、保険適用外なので患者さまには大きな経済的負担がかかります。日本の制度や医療ポリシーを踏まえた上で、治療の効果やリスクを十分に検討し、保険会社や患者さまと相談して最良の選択肢を見いだすことが大切です。医療費負担の一覧や各種保険の特徴を比較しながら、自分の健康状態と経済状況に合った方法を選ぶことが求められます。
先進医療が自由診療に該当する場合のメリットとデメリット
自由診療を利用すると、高度な技術や最新の薬剤など、従来の保険診療では受けられない方法を行えるメリットがあります。日本で未承認でも海外では承認済みの治療を行えるため、患者さまへの効果が大きい可能性も広がります。ただし、公的保険が適用されない分、医療費は高額になりやすく、経済的負担が増大します。また先進医療の場合、十分なデータがそろっていないケースもあり、安全面でのリスクや未知の有害事象を考慮しなければなりません。がん保険や医療保険も一部の自由診療には対応しないことがあり、費用を患者さま自己で全額支払う必要が生じることがあります。提案を検討する際は患者さまの経済的負担も考慮しながら、治療目的や費用対効果を見極めることが大切です。海外の情報や貴院の方針を踏まえつつ、現実的な負担を把握したうえで治療を選びましょう。
自由診療のポイントを総まとめ
保険診療と比べて治療の制限が少なく、多様な選択肢を提供してくれるのが自由診療です。患者さま自身の身体や病気に合わせた柔軟な行為が実施でき、日本では未承認の先進治療を受けられる点も見逃せません。公的保険が使えないため自己負担が全額になるのは大きなデメリットですが、求める効果を最優先できるメリットはあります。患者さまが自由診療に踏み切るかどうかは費用やリスクをどこまで許容できるかで変わります。特にがん治療などでは海外の技術や新薬をいち早く取り入れられる可能性がある一方、厚生労働省による承認がない治療法も含まれる点に注意が必要です。医療費の高さから予算管理が重要になり、全額負担の負荷が経済状況に影響することも考えられます。患者さまとしっかりと相談し、必要な検査やリスク管理を丁寧に行いましょう。十分な情報を把握したうえで計画的に進めることが、安全性を守りつつ患者さまに合った治療を提案、行う近道です。
自由診療を選ぶ前にチェックすべき項目と安全方針
研究段階の方法や日本での承認データが乏しい治療法も含まれるため、高額な費用をかけても期待された効果が得られない可能性があります。安全面が十分に検証されていない場合も考えられるので、副作用や有害事象が起きたときにどのように対応するかを事前に確かめ、貴院の方針を定め、クリニック全体できちんと共有することが大切です。たとえば、未報告の合併症が生じるかもしれません。医療機関によっては独自の管理体制を用いていることが多いため、貴院ではどのような方針をとるかをよく確認する必要があります。経済面も考慮したうえで、患者さま自身が納得できる環境を整えることが望ましいです。思わぬリスクを最小限に抑えるため、医師との話し合いを重ねて費用対効果や安全性を確認し、患者さまが十分に理解するまで説明を行うことで安心につながります。
オンライン診療導入ガイド
【こんな方におすすめ】
- オンライン診療の導入を検討している
- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい
- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない