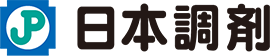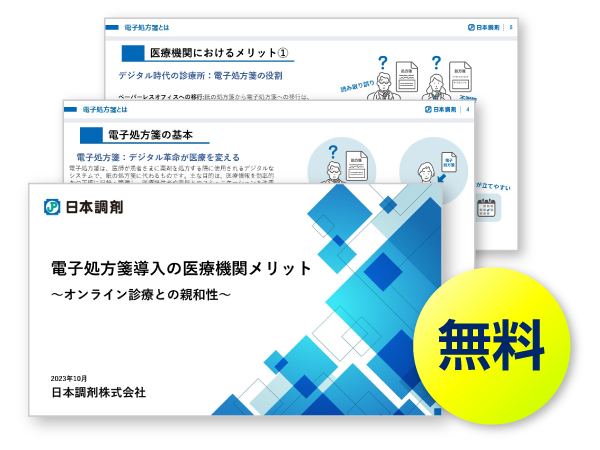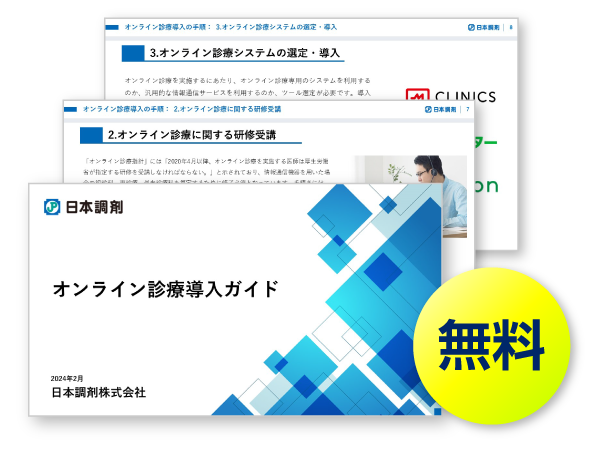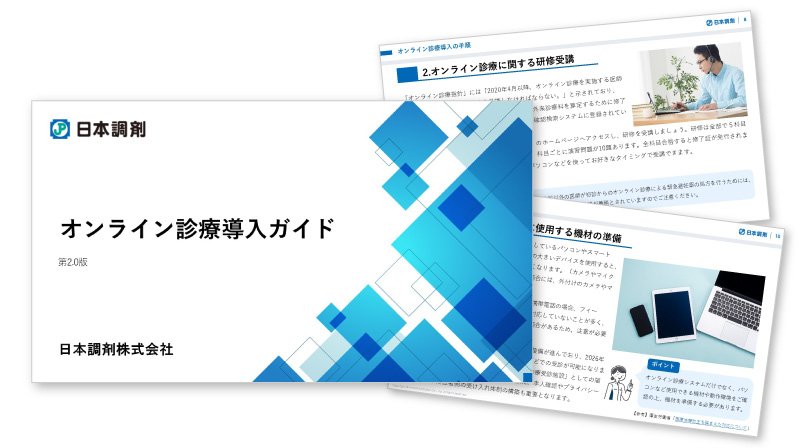近年、医療機関を標的とするサイバー攻撃が相次いでいます。診療所やクリニックでは電子カルテやオンライン診療ツールなど医療システムの利用が拡大し、個人情報や患者データのセキュリティ対策が経営と業務運用の重要課題となっています。ランサムウェアによるインシデントは診療やサービス提供の停止、経済的損失にも直結しかねません。記事では厚生労働省や関連機関が発信するセキュリティガイドラインの解説、実際のシステム管理や研修、最新IT技術の活用法などを取り上げます。経営リスクを最小化し、医療情報を安全に運用するための具体的な対策をお伝えします。
目次
日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた
「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。
医療情報セキュリティの重要性と背景を徹底解説【2025年最新動向】
医療情報セキュリティは現代医療で極めて重要な課題となっています。医療機関が管理する個人情報や診療データは、サイバー攻撃の主な標的となりやすく、その漏洩や改ざんが発生した場合、患者さまや医療従事者双方に多大な被害や信頼喪失をもたらす恐れがあります。このリスクの高まりを受けて、多くの医療機関や関連機関では、実態調査やリスクアセスメントに基づいた具体的なセキュリティ対策の導入が進んでいます。例えば、アライドテレシスはこれまでの経験や事例をもとに「12種類のセキュリティリスク」を分類し、セキュリティ診断によるリスクレベル判定や対策優先度の設定、個別施設に応じた対策提案サービスを提供しています。特に、ITシステムの運用やネットワーク、一元管理する運用体制の整備と教育研修の定期実施などは、安全を確保するうえで不可欠です。加えて、厚生労働省や関係省庁による最新ガイドラインの順守も要求されており、医療事業における法的・技術的要件が一層厳格化されています。実際の現場では、インシデントの早期発見や迅速な報告体制の構築も求められており、そのための支援窓口や資料も提供されています。セキュリティ対策の導入状況やリスクレベルは施設ごとに異なりますが、全体として医療情報の安全確保、患者保護、事業継続の観点からは、リスク評価に基づく継続的な対策強化と実運用に即した支援策の導入が極めて有効です。まずは自院のリスク状況を資料で確認し、必要な対策の検討・強化を進めていくことが推奨されます。資料ダウンロードやお問い合わせも積極的に活用するとよいでしょう。
医療情報を狙うサイバー攻撃の現状と想定される被害の深刻度
医療機関が受けるサイバー攻撃は年々増加しており、想定される被害は非常に深刻です。特にランサムウェアや標的型攻撃による医療情報システムの停止は、診療停止や患者データの消失など、経営全体に甚大な影響をおよぼします。例えば2022年に大阪の急性期・総合医療センターが2ヶ月間も診療停止に追い込まれ、徳島県つるぎ町立半田病院でも一部診療停止となった事例が知られています。これらの事案から、サイバー攻撃が単に情報漏洩や一時的な業務停止を招くだけでなく、地域医療体制や社会全体に影響を与えるリスクが現実化していることがわかります。医療機関にとっては、セキュリティ対策の強化だけでなく、事業継続計画(BCP)や緊急時対応体制の構築といった幅広いリスク管理が不可欠です。さらに、専門人材の確保やITシステム自体の防御力向上も急務と言えます。リソースや運用体制の充実が遅れていると、攻撃発生時に対応が遅れ、復旧も長期間に及ぶ可能性があります。そのため経営層もサイバー攻撃を自然災害同様の経営リスクと認識し、継続的な教育・投資・外部支援の活用を検討すべきです。今後も被害動向を注視しつつ、定期的なセキュリティチェックと最新対策への更新が不可欠となります。
【参考】厚生労働省「医療分野のサイバーセキュリティ対策について」
病院・診療所など医療機関のセキュリティ体制構築に必要な基本方針
病院・診療所をはじめとする医療機関のセキュリティ体制構築には、体系的な方針と現場での実践が両立されることが求められます。まず最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」や「サイバーセキュリティ対策チェックリスト」に基づき、自院のセキュリティリスクを特定し、そのレベルに応じた優先対策を明確化することが重要です。ネットワークやサーバー、外部記憶媒体へのアクセス管理、個人情報の取り扱い、システムの定期的な点検やアップデートなど、具体的な運用ルールを策定し、システム保守業務とあわせて責任の所在を明確に管理しましょう。加えて、院内外で発生しうるインシデント発生時の連絡や初動対応体制も整備することが欠かせません。職員一人ひとりのセキュリティ教育・研修も継続的に実施し、サイバー攻撃の最新手口やリスク意識の向上に努めることが求められます。こうした方針の下、医療機関ごとの経営資源や状況に合わせた現実的な対策を段階的に導入すると同時に、外部の最新事例や改定資料も活用しながら、必要な見直しやアップデートを怠らないことが重要です。
オンライン診療時代の医療情報セキュリティ:新たなリスクと対策
オンライン診療がもたらすセキュリティリスクの増加
オンライン診療の普及は、患者さまの利便性を高める一方で、医療情報を取り扱う環境を多様化させ、新たなセキュリティリスクを生み出しています。具体的には、クラウド上での診療データ管理、患者・医師双方の自宅などからのリモートアクセス、ビデオ通話システムの利用などが、これまでの院内ネットワーク中心のセキュリティ対策だけでは対応しきれない課題を提示しています。Web会議システムの脆弱性や、患者側のデバイス(PC、スマートフォン)がマルウェアに感染しているリスクなども考慮が必要です。
オンライン診療を安全に運用するためのセキュリティ対策
オンライン診療の導入・運用においては、その利便性と引き換えに新たなセキュリティリスクが生じる可能性があります。患者さまの個人情報とクリニックの信頼を守るため、以下の2つの側面から対策を徹底することが不可欠です。
①オンライン診療システム選定時のセキュリティチェックポイント
安全なオンライン診療を継続するためには、導入するシステムのセキュリティ機能が非常に重要です。システム選定の際は、以下の点を確認しましょう。
-
通信の暗号化:患者と医療機関間の通信が常に暗号化されているかを確認してください。
-
アクセス制御:権限のないアクセスを防ぐための厳格な認証機能(多要素認証など)が備わっているか。
-
データ保存場所と管理体制:患者データがどこに保存され、どのように管理されているか、クラウドベンダーのセキュリティ体制も十分に確認する必要があります。
-
ログ管理:誰が、いつ、どの情報にアクセスしたかの記録が適切に残されているか。
-
監査体制:定期的なセキュリティ監査が実施されているか、その結果が公開されているかなどを確認しましょう。
②オンライン診療における従業員教育の強化
リモートワーク環境下での情報セキュリティ意識の徹底は、サイバー攻撃防止において重要な役割を果たします。技術的な対策だけでなく、人的な脆弱性への対応が不可欠です。
-
個人情報保護の徹底:個人情報を含むオンライン診療データを扱う際のルールを徹底します。
-
ネットワーク環境の安全性確保:自宅Wi-Fiなどの利用時も、安全なネットワーク環境を確保するためのガイドラインを策定・周知します。
-
サイバー攻撃への注意喚起:フィッシング詐欺や不審なメールに対する注意喚起と、具体的な識別方法・対処法を周知します。
-
使用デバイスのセキュリティ対策:オンライン診療に使用するデバイス(PC、スマートフォンなど)のOS・ソフトウェアを常に最新化し、ウイルス対策ソフトの導入と定期的なスキャンを義務付けます。
これらの対策を講じることで、オンライン診療におけるセキュリティリスクを最小限に抑え、安全で信頼性の高い医療提供が可能になります。
医療情報システムに関するガイドライン改定と厚生労働省の新たな対応策
医療情報システムのガイドライン改定と厚生労働省の対応策は、医療機関における情報セキュリティの水準向上に直結する重要なテーマです。医療業界のデジタル化・電子カルテ利用拡大を背景に情報漏洩リスクやサイバー攻撃が増大し、法規やガイドラインの継続的な見直しが不可欠になりました。
厚生労働省は「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」を令和5年5月策定し、この改定により、オンライン資格確認の原則義務化と、それに伴う医療機関の情報システム利用環境の変化に対応するため、より実践的かつ体系的なセキュリティ対策を求める内容に強化されています。
変更点を把握し、リスク評価を実施、現場対応方針やマニュアルを改訂、実際の診療・業務へ反映することが極めて重要です。厚生労働省からはガイドライン資料のダウンロードや現場向け解説、点検リストも提供されているため、積極的に活用してセキュリティ体制を強化しましょう。
【参考】厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版」(令和5年5月)
3省2ガイドラインの概要と現場対応のポイント
医療情報システム関連のガイドラインは、厚生労働省・経済産業省・総務省の連携で更新されてきました。従来は合計4つのガイドライン(3省4ガイドライン)が存在していましたが、クラウド技術の普及や管理対象拡大を受け、総務省の2つのガイドラインが統合され、その後「クラウドサービス事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン」として整理されました。最終的には事業者負担や運用現場の利便性向上の観点から、2018年に経済産業省と総務省のガイドラインも統合され、現在は「3省2ガイドライン」となっています。最新版(第6.0版)では、医療情報を取り巻く環境変化に伴ってセキュリティ方針が強化され、サイバーセキュリティ、ネットワーク管理、クラウド利用時の安全管理策など具体的な対策ポイントが明記されています。現場での実践では、これらのガイドラインに沿った内部規定や外部委託先の選定・監督、アクセス権限や個人情報の管理方針の策定、定期的な運用チェックと教育がポイントです。自院の業務やシステム構成を改めて確認し、対応漏れのない運用体制を構築するとともに、法令改定や新ガイドラインへの随時対応が肝要です。
サイバーセキュリティ対策チェックリスト2025年度版の活用方法とは
サイバーセキュリティ対策強化にあたり、2025年度版の「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」の活用が不可欠です。この資料は、医療情報安全管理ガイドラインの中でも重要項目に特化し、診療所や薬局、関連事業者ごとの具体的な確認ポイントをチェックリスト形式で示しています。法令に基づく立入検査でも確認が義務付けられるようになり、事実上、対策実施が強く求められる内容となります。法的根拠のある文書として、チェックリストの回答や記入状況を点検することが必須となり、検査時に備えて記録と運用状況を常に最新化しておく必要があります。業務繁忙期や人員交代が発生した際でも漏れのない運用を実現するため、定期的な内部レビューや実地確認の実施もポイントです。普段からこのリストを用い、システム設定やネットワーク機器、担当者教育などまで網羅したセキュリティ体制チェックを徹底しましょう。新たに発表された2025年度版のチェックリストをダウンロードして、自院の現状を再確認し、速やかに現場へ反映していくことが大切です。
【参考】厚生労働省「令和7年度版 医療機関におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」
医療機関で実施すべきセキュリティ対策とシステム管理の具体的方法
医療機関におけるセキュリティ対策には、徹底した現状把握、リスクマップ作成、効果的なシステム管理が欠かせません。最新の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」や「サイバーセキュリティ対策チェックリスト」を活用し、状況に応じた対策を段階的に導入することが基本です。アクセス権限管理の徹底、パスワードの強化・定期変更、外部機器接続制限、ウイルス対策ソフトやファイアウォールの適切な設定が重要であり、物理的セキュリティも見逃せません。患者さま・職員の個人情報や診療データは厳格に分離・保護し、適時バックアップを作成、安全なネットワーク環境下で運用することが求められます。また、保守・点検や運用記録の管理、インシデント発生時の初動対応体制も組織全体で整備しましょう。教育・研修制度を定期導入し、新たなサイバー攻撃の動向や最新事例を職員全員が理解できる体制を整えることも大切です。委託先や外部ベンダーとの連携、厳格な契約・責任範囲設定についても確認を怠らないことが求められます。自院のセキュリティ状況を定期的にセルフチェックし、必要に応じて専門機関の外部診断や資料請求も検討してください。各種資料やガイドラインの内容を反映した運用ルールを構築し、安全かつ継続的な医療サービスの提供を目指しましょう。
強固なパスワード設定とUSBなど外部機器の接続制限徹底の重要性
パスワード設定の強化と外部機器(特にUSBメモリ等)の接続制限は、医療機関のセキュリティ対策において極めて重要なポイントです。医療情報システムは患者さまの個人情報や診療記録を扱うため、不正アクセスやランサムウェア感染時のリスクが高いことから、基本となる運用ルールの徹底が不可欠となります。パスワードは英数字・記号を組み合わせた複雑なものを採用し、定期的な変更を義務付けることで、総当たり攻撃や流出リスト対策に有効です。一方、USBなど外部ストレージの利用制限は、ウイルス感染や情報流出の主な経路となるため、端末ごとに設定を強化し不正な持ち出しを禁止する運用が推奨されます。厚生労働省が公表した最新版ガイドラインとチェックリストでも、これらの項目が重要管理事項として取り上げられています。実務では、係る規定を職員全員に徹底し、違反時の対応マニュアル整備やシステム管理者による監査も必要です。ITセキュリティの意識向上と日常的な運用チェック体制で、院内の安全性向上を図りましょう。
インシデント発生時の初動対応と厚生労働省への報告方法・流れ
インシデントが発生した際、最初に取るべき対応は被害拡大の防止と迅速な状況把握です。医療機関の場合、ランサムウェア感染やウェブサイト改ざん、機器障害など様々なサイバーインシデントが想定されますが、初動段階ではネットワーク隔離や該当システムの利用停止、影響範囲の確認を迅速に行う必要があります。次に厚生労働省委託事業で設けられている初期対応支援窓口や専門機関に相談し、現地訪問やオンライン支援を受けることで、より的確な対処方針を決定します。重大インシデントの場合は、厚生労働省への報告が必須となり、定められた様式や手順に従って関係資料を準備し、期日内に連絡・報告することが求められます。このような対応フローを院内マニュアルとして事前策定し、職員への教育・訓練と年次見直しを行うことで、万一の際にも被害を最小限にとどめることができます。最新の支援体制や報告様式は、厚生労働省のサイトや関連支援事業の運用ページから確認のうえ、平時から体制整備を怠らないようにしましょう。
電子処方箋導入の医療機関メリット
~オンライン診療との親和性~
【こんな方におすすめ】
- これから電子処方箋を導入したい
- 電子処方箋の仕組みを知りたい
- オンライン診療に電子処方箋を活用したい
サイバー攻撃防止のための職員教育・研修と医療現場での実践事例
医療機関のサイバーセキュリティ強化には、職員の教育・研修体制の整備・充実が不可欠です。技術面のみでなく、人的な脆弱性への対応がサイバー攻撃防止において重要な役割を果たします。厚生労働省は「医療機関向けセキュリティ教育支援ポータルサイト(MIST)」を設置し、医療経営者、現場従事者、関連スタッフ向けに役割ごとの研修カリキュラムや教育コンテンツを段階的に提供しています。例えば、管理者向けにはリスク評価やポリシー策定、職員向けには実際の事故事例をもとにしたフィッシングメール対策やシステム運用のポイント、IT担当者向けにはネットワーク管理や機器設定の注意点など、幅広い内容が網羅されています。加えて、サイバーインシデント時の相談・初動対応窓口も用意され、現場で直面した事案に即応できる体制が構築されています。こうした制度の活用により、各組織のサイバーリスク低減だけでなく、実際の被害防止や事業継続面での備えが大幅に強化されます。実践事例としては、経営層主体での定期研修、インシデント対応演習の実施、全職員へのオンライン教材反復受講が効果的であり、継続的な取り組みとして推進される傾向にあります。新しいセキュリティ知識を全員が共有し、実際の業務に反映していく姿勢が、総合的なセキュリティ水準向上を実現します。
研修制度導入によるサイバーリスク低減策と効果的な運用ポイント
研修制度を導入することで、医療機関のサイバーリスク低減が期待できます。経営層、システム管理者、現場職員など、役割や専門性に応じた研修プログラムを設定し、e-learningなど何度でも受講できる環境を整えることで、知識の定着と意識向上が促されます。特にフィッシングメールを見抜く訓練や、パスワード・情報取り扱いに関する規定の周知徹底は、日常的なリスクを大きく抑えるポイントです。継続的な受講と理解度評価、最新事例やインシデント情報の速やかな共有も重要です。こうした教育体制は単なる「対策の説明」ではなく、現場で自立的なセキュリティ行動を取れる人材を育成する点に大きな価値があります。組織の成長やシステム変更にあわせて内容を随時見直し、教育効果の検証にも取り組むことで、全体として堅牢なセキュリティ体制が維持できます。
最新IT技術を活用した医療情報の安全な運用と患者データ保護の工夫
最新IT技術を活用した医療情報の安全運用は、病院経営や患者保護の観点から非常に重要なテーマです。クラウドサービスや仮想化技術、暗号化通信、セキュリティ診断ツールといったITインフラの導入によって、医療機関全体の管理効率やセキュリティ強度は大きく向上します。患者さま・職員データの不正アクセス対策としては、多層防御型ネットワークの構築や、権限分割、通信ログ管理といった統制措置が効果的です。また、IT資産全体のリスト化と可視化、定期的なソフトウェアアップデート、外部との安全なデータ共有やクラウドバックアップの活用も安全確保には欠かせません。インシデント発生時の影響を最小限に抑えるため、医療情報や業務データの定期バックアップと復旧訓練の実施が重要です。現場ではITソリューションベンダーと連携し、最新のセキュリティサービスやシステム改善策を随時取り入れることが推奨されます。ITインフラ診断や情報セキュリティ対策の見直しにより、患者データ保護の工夫を継続的に積み上げましょう。今後も現場担当者は、最新動向を把握しつつ、自院に最適な技術導入を進めてください。
IT資産管理ツールや二要素認証の早期導入による安全性強化策
IT資産管理ツールや二要素認証の導入は、医療機関が直面するサイバー攻撃リスクを軽減する有効策です。近年、ランサムウェア感染によるシステム停止やデータ暗号化被害が全国各地の病院で発生しており、こうした攻撃ではシステム管理の不備や認証手続きの脆弱性が悪用される傾向があります。資産管理ツールの導入によって、院内すべてのネットワーク機器や端末の設定状況・脆弱性を即座に把握し、アップデートや不正端末排除を迅速に行うことが可能です。また、二要素認証は不正アクセスの防御力を飛躍的に高め、パスワード漏洩時にも被害拡大が防げます。厚生労働省ではガイドライン改定後、都道府県による立入検査や対策状況のチェックも強化しているため、これらのシステム的対策は経営・実務両面で急務と言えるでしょう。現場では早い段階で導入検討を進め、運用マニュアルや職員教育とあわせて有効活用するべきです。
医療機関がサイバーセキュリティ強化のため今後取り組むべき課題と展望
医療機関がサイバーセキュリティ強化のために今後対応すべき課題は多岐にわたります。まず最大の課題は、サイバー攻撃が「病院システム全体の停止」や「地域医療崩壊」に直結しかねない重大リスクであることを全職員が認識することです。2022年や2021年のランサムウェア事件を踏まえても、システム復旧や診療再開には数週間から数ヶ月を要する場合があり、その影響は病院経営だけでなく周辺地域の患者さまや連携医療体制にも波及します。今後は、診療情報やネットワーク機器の安全確保に加え、インシデント対応プロトコルの策定、初動対応力の向上、BCP(事業継続計画)の整備が喫緊の課題となります。ITシステム・セキュリティ対策の予算確保や専門人材の教育も継続的に推進すべきです。最新のセキュリティ技術や教育プログラムを積極的に導入し、厚生労働省等のガイドラインやチェックリストを現場で生かす運用力が問われています。外部支援やセキュリティ診断サービスと連携し、経営層主体での推進体制を整える必要もあります。今後もサイバー攻撃手法は進化するため、医療情報と患者さま・医療従事者を守るための体制強化を途切れなく実施することが肝要です。
まとめ
医療情報セキュリティ対策のあり方は、患者さまの個人情報・診療データの保護はもちろん、医療機関自身の社会的信頼や経営の安定にも直結します。サイバー攻撃は年々多様化・巧妙化しており、一度のインシデントが診療停止や事業継続リスクにつながる事例も増えています。安全なシステム運用には、厚生労働省などのガイドラインや最新版のチェックリストの内容を日々点検し、強固なパスワード設定や外部機器制限、最新ITインフラの導入、教育・研修制度の徹底が欠かせません。加えて、インシデント初動対応フローや迅速な報告体制の整備、クラウドやリモートワーク活用時の安全確保、外部企業と連携した現場支援も重要です。院内の誰もがセキュリティリスクを他人事とせず、職員一人ひとりが責任感を持ってルール実践に取り組むことで、組織全体の安全性が飛躍的に高まります。自院の現状に合わせてITインフラや運用ルールの見直し・改善に主体的に取り組みましょう。まずは現状把握とリスク評価を行い、必要に応じて専門家の支援や資料活用を進めることで、患者さまと医療機関の双方を守る堅牢なセキュリティ体制構築を目指してください。
あなたの病院は大丈夫ですか?次のアクションとして、自院のITインフラストラクチャーの再点検や、医療機関向けソリューション・情報セキュリティ対策の導入を積極的にご検討ください。