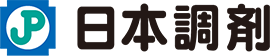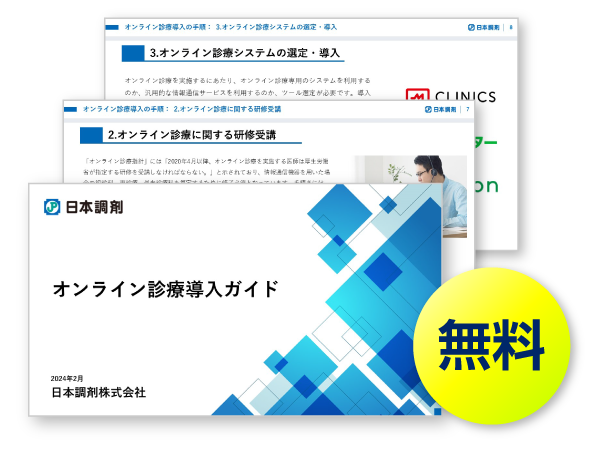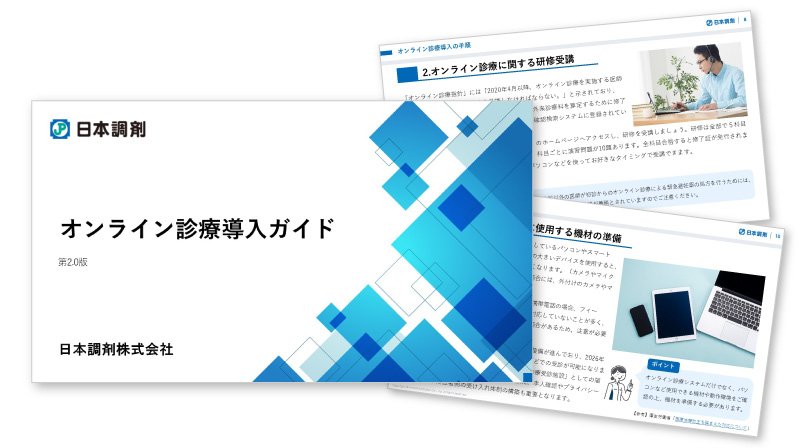診療に欠かせないカルテの保存期間や保管方法は、法令遵守や医療安全を考えるうえで重要です。患者さまの情報を適切に保持し、保険請求や廃棄のタイミングを理解することが求められます。本記事では紙カルテと電子カルテの比較やセキュリティ対策、電子署名のポイントなどを解説し、医療データの安全管理を実現する方法を紹介します。
目次
日本調剤では、オンライン診療の導入を検討されている方に向けた
「オンライン診療導入ガイド」をご用意しております。
カルテの保存期間は何年?法的根拠や理想を詳しく解説
カルテ(診療録)の保存期間は法律上5年間と規定されていますが、20年間や永久保存を選ぶ医療機関も増えています。診療の経過を長期的に確認できれば、患者さまの治療方針を適切に見直しやすくなり、安全な医療提供にも役立ちます。紙カルテの場合、物理的な保管スペースと管理コストがかさむため、電子カルテの導入も効果的です。外部機関へデータを委託する場合はセキュリティ対策やガイドラインの確認が必要ですが、適切に対応すれば廃棄や紛失のリスクを減らすことができます。開業時やシステム入替のタイミングで紙カルテを電子化することで長期保存と情報保護を両立しやすいのではないでしょうか。患者さまの記録を確実に残すことで、トラブル回避や診療の質向上に大きく寄与します。
カルテ保存における5年ルールの背景と安全管理の確認ポイント
法律で定められた5年ルールは、保険請求にも必要なため軽視できません。紙カルテは紛失や老朽化のリスクがあるため、安全管理が重要となります。近年は電子カルテへ移行する病院も増えており、改ざん防止やアクセス権限の設定に気を配り、真正性と見読性を確保する方法を取りましょう。
- 責任者の役割を明確にする
- バックアップやセキュリティ対策を徹底する
これらを実践することで、5年間の保存義務と患者情報の保護を両立できます。
紙カルテと電子カルテの保存方法と期間差異を徹底比較
紙カルテは物理的保管が必要で、スペースや管理コストがかかります。電子カルテならクラウドや院内システムでの保管が可能になり、データ共有やレセプト処理を効率化することができます。紙では字の読みにくさや紛失リスクがあり、二重入力の手間が生じる場合もありますが、電子では入力ミスが減り、記録を見直しやすいメリットがあります。保管期間終了後は、紙カルテは廃棄時も注意が必要ですが、電子カルテはセキュリティ強化で長期保存を容易に実現できます。
病院・クリニックで求められる文書保管とセキュリティ管理の基本
医療法や医師法などの規則により、カルテや検査結果などの文書の保存は義務とされています。期限を過ぎた書類は破棄しても違法ではありませんが、医療行為の正当性を示す重要な資料として残しておくことが望ましいです。保存期間は診療が終了した日から数えるため、この起算点を誤ると不足期間が生じます。患者さまからの信頼を失わないように、改ざんや紛失を防ぐ方法を検討し、担当者とルールを明確化しましょう。
- 適切な保管場所で紛失リスクを回避
- 電子カルテ導入による自動バックアップやアクセス制限の設定
これらを全体方針として運用すれば、文書の安全管理が強化されます。
診療記録の保管義務と保険請求に関する重要な注意点
診療記録であるカルテは医師法の規定により作成が義務付けられ、保険請求の基礎資料としても欠かせません。患者さまの住所や氏名、症状、治療内容などが正確に記録されていなければ、保険請求時に根拠が示せずトラブルにもつながります。電子カルテを利用するなら、署名やパスワード管理などのセキュリティ対策を定め、真正性を保つ仕組みを導入することが必要です。紙カルテでも記載不備は不利益が大きいため、保管期間と併せて内容もしっかり確認する必要があります。
保存期間超過後のカルテ廃棄と患者情報保護の安全対策
カルテの法定保存期間が終了して廃棄を検討する際は、患者さまの個人情報を守るためにも適切な方法が求められます。紙カルテは溶解やシュレッダーなど専門業者への委託が効果的で、電子カルテの場合も機器の廃棄時にデータを完全削除し、不正アクセスを防ぐセキュリティ対策を講じましょう。保険請求後であっても、カルテをしばらく保管しておくことで訴訟発生時には医療機関としての責任を果たすことができます。
オンライン診療導入ガイド
【こんな方におすすめ】
- オンライン診療の導入を検討している
- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい
- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない
電子カルテ導入によるメリットとセキュリティ面での注意すべきポイント
電子カルテを導入すると、紙カルテの保管スペースを削減でき、検索やレセプト請求がスムーズになるなどのメリットがあります。医師や看護師は患者さまの診療情報を迅速に共有可能となり、医療の質や作業効率が上がります。しかし、セキュリティ面での対策を怠ると、不正アクセスやデータ改ざんが発生する場合があるため注意が必要です。
システムの定期的なアップデートとバックアップの実施や、電子署名やログ監査で情報の真正性を確保することで、電子カルテの利点を最大限に活かしながら患者さまデータの保護をより強固にできます。
電子署名や真正性の確保に必要な手続きと具体的な流れ
スキャンした文書は改ざんの有無が判別しにくいため、電子署名とタイムスタンプを付与して真正性を保証します。原紙の代わりとして認められるには、作成者や時刻、変更の有無を明確化することが必要です。手続きを正しく踏めば紙カルテの保管スペースが大幅に減り、セキュリティリスクも抑えられます。
クラウド型電子カルテとオンプレミス型の比較・メリット
クラウド型電子カルテは、初期費用や機器の更新コストを抑えやすく、データセンターで常に厳重管理されるため、長期的なカルテ保存にも向いています。災害時のBCP対策としても有効で、外部バックアップを定期的に行うことでデータ消失を防げます。一方、オンプレミス型は自院内のサーバーで運用するため、ネットワーク障害時でもある程度院内で診療を継続できる利点があります。どちらを選ぶにしても、厚生労働省のガイドラインや医療機関のポリシーに沿って安全管理を行い、コスト面とのバランスを考慮することが重要です。
オンライン診療時の電子カルテ利用と具体的トラブル対策
オンライン診療でも電子カルテを活用すれば、離れた患者さまのデータを即時に確認でき、診療効率が上がります。ただし、紙カルテを電子化する際には「真正性」「見読性」「保存性」の3原則を守る必要があります。問題なく電子カルテを利用するためにも次のことを徹底しましょう。
- 故意の書き換えを防止する仕組みを設定
- 医療情報を肉眼で読み取れる形式を維持
- データのバックアップを適切に行い保存期間中の破損を防ぐ
電子カルテの種類や導入のメリット・デメリットについてはこちらの記事でも解説しています。
【関連記事】電子カルテ活用術!医療業界の変革への道
閉院や長期保存への対策:カルテ保管ルールと保護ポリシーを再確認
診療期間の終了後もカルテは5年間、レントゲンフィルムは3年間の保存義務があります。これは閉院した場合も同様です。適切な管理体制を整えることで、後々に発生しうる訴訟やクレームへの対応が容易になります。保存期限が切れたとしても重要な証拠となる可能性があるため、すぐに破棄することはおすすめできません。
- 物理的な保管場所や電子化システムを用い、長期的な安全管理を行う
- 過去の診療データを検証できるようにしておき、患者さまとの信頼関係を維持
こうした方策を取り入れることで、閉院後もカルテの保管と情報保護を確実に実行できます。
閉院した場合に必要なカルテ保管と委託先選びの注意点
閉院後も5年間のカルテ保管義務は変わりません。適切な保管先を確保できない場合、専門業者への委託を検討するとよいでしょう。その際は委託先のセキュリティ対策と実績を確認し、院内ポリシーの遵守も徹底する必要があります。保管期限を過ぎても過去の医療行為の証拠となるため、急いで廃棄するのは避けたほうが安全です。患者さまへの説明責任も含め、閉院後のトラブルを防ぎましょう。
紙カルテのスキャン活用で可能なスペース削減と費用対策
紙カルテをスキャンしてデータ化すれば、保管スペースと費用を大幅に削減できます。2005年施行のe-文書法により、一定要件を満たせば電子文書としての保存も認められています。
- 電子署名やタイムスタンプで改ざんを防止
- JPEGやPDFなど汎用的な形式で保管し可読性を担保
- 外部委託時はセキュリティ対策と監査体制を確認
これらを行うことで、紙カルテの保管を減らすことができ、管理の負担も軽くなります。
レセプトや検査結果などその他書類の保存年数と具体的運用
レセプトや検査結果などの書類も法的に保存義務があり、電子カルテやレセコン(レセプトコンピューター)を利用すれば効率的に運用可能です。ただし、電子データは変更が容易なため、改ざん防止やバックアップの仕組みを整える必要があります。厚生労働省のガイドラインにある「真正性」「見読性」「保存性」を満たすよう、運用面と技術面を両立して対策しましょう。
- セキュリティポリシーを策定し、適切なアクセス権限を設定
- 紙書類廃棄時も漏えいリスクを考慮し、専門業者への処理委託などを検討
これらを徹底すれば、患者情報を安全に保持できます。
まとめ:カルテ保存期間と実践的管理の重要ポイントを改めて確認
カルテの保存期間は、一連の診療が終了した日から5年間(レントゲンなどは3年間)と定められています。紙・電子どちらの場合も、この起算点を誤らないよう注意が必要です。保管の際は、長期保存に対応できるセキュリティ対策や改ざん防止の仕組みを整えましょう。診療所やクリニックで開業を予定している方や、システムの導入や見直しを検討している方は、今回のポイントを踏まえてカルテ管理を再点検してみてはいかがでしょうか。保管・廃棄の手順を明確にし、患者さまとの信頼をより強固にするためにも、今後の取り組みにぜひご活用ください。
オンライン診療導入ガイド
【こんな方におすすめ】
- オンライン診療の導入を検討している
- オンライン診療導入の基本的な手順を知りたい
- オンライン診療を導入したいが、なにから始めたらいいか分からない